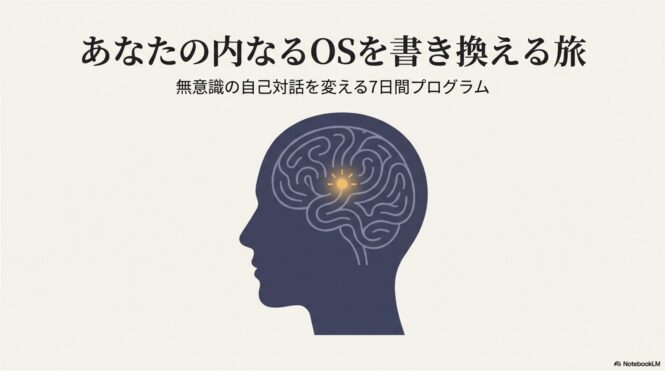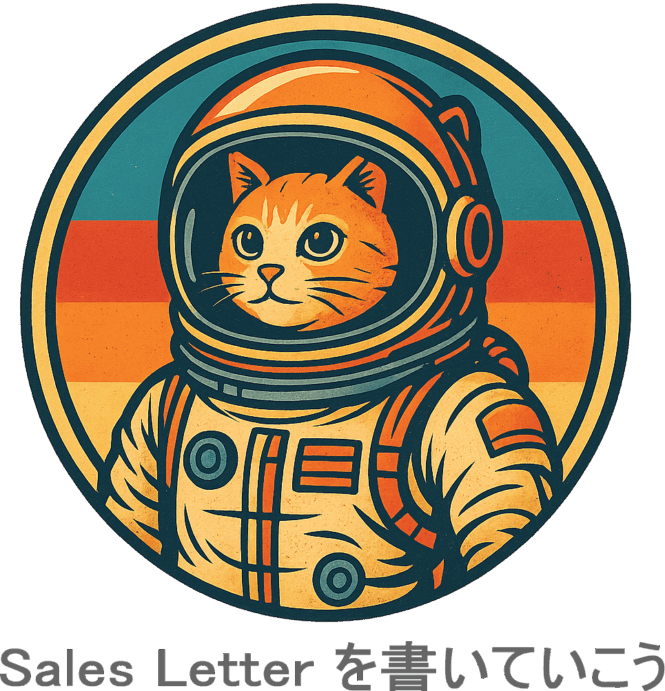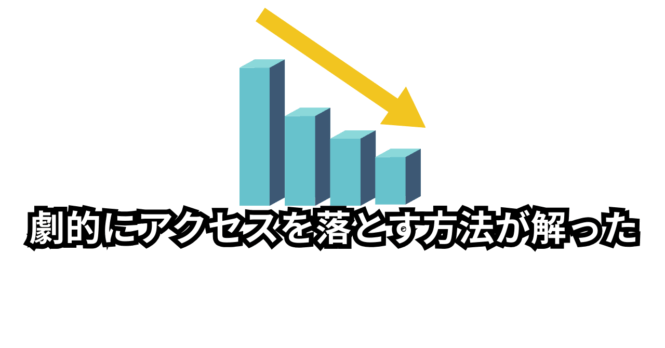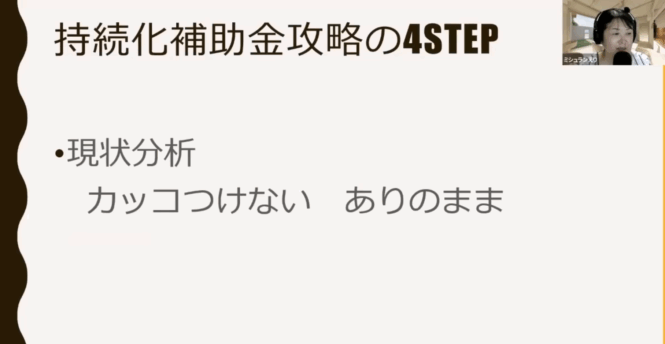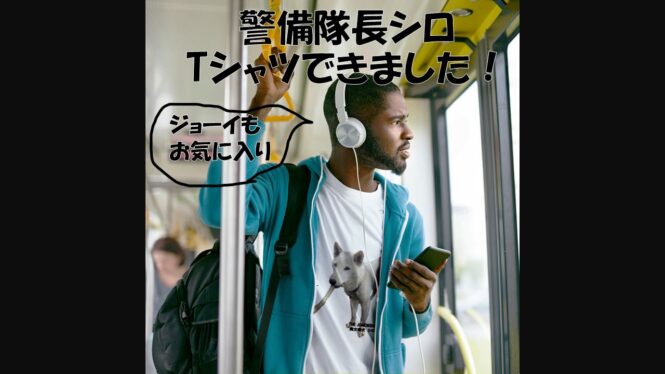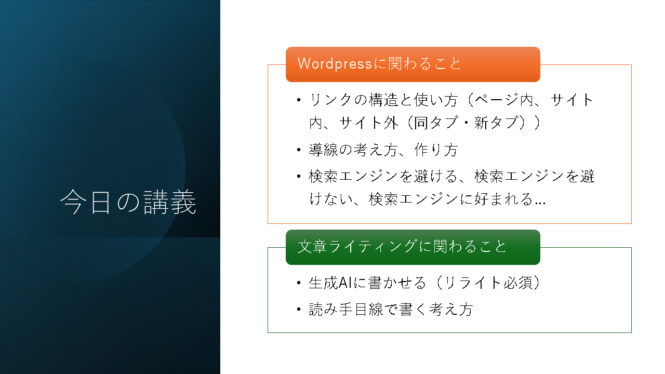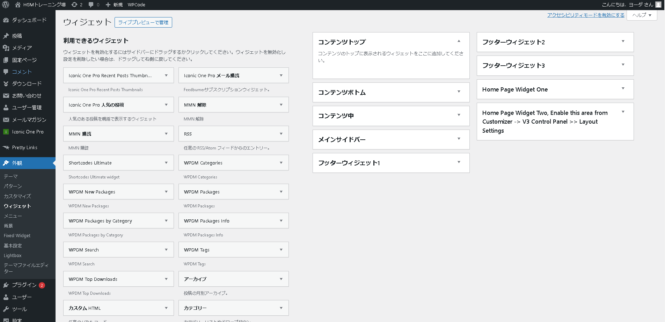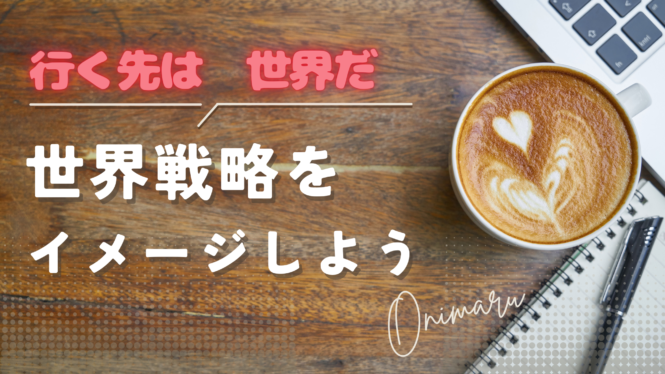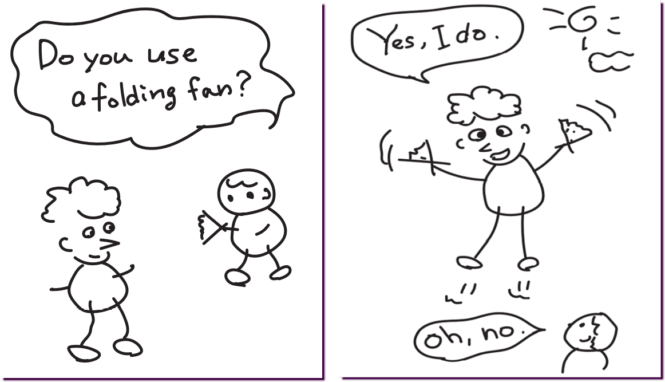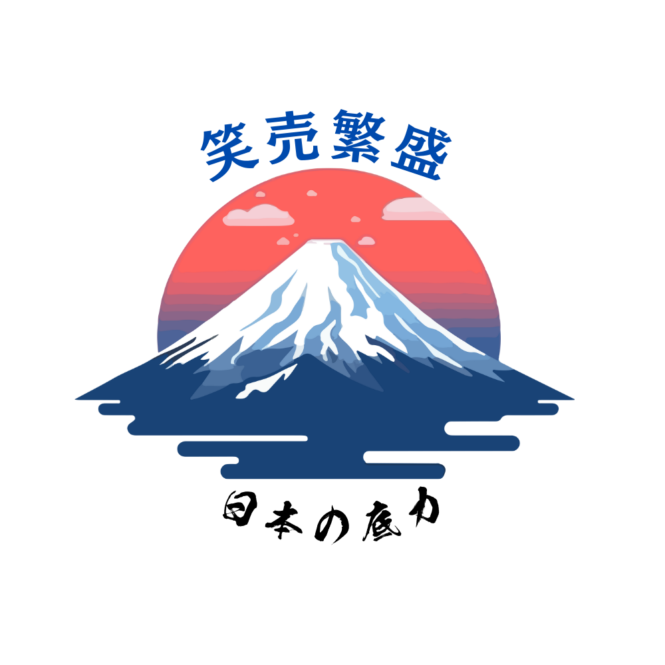NotebookLM を使い、自分の知力を引き上げる学習をしよう
NotebookLMを学習ツールとして使うことをお勧めします。
- 簡単に要点整理ができる
- 理解までの時間が短縮できる
- 自分用の問題集も作れる
ここでは初心者がまず始めるべき3つのステップを動画と文字情報で解説します。
動画解説
文章解説
①NotebookLMにアクセスし、ノートブックを作成する
- https://notebooklm.google.com/ Googleアカウントでログインします。(18歳以上が推奨されています)
- NotebookLMにアクセスし、「新しいノートブック」を作成します。
- 作成したノートブックに、まとめる情報に合わせたわかりやすいタイトルをつけます。(例:「〇〇プロジェクト資料」「〇〇に関する研究資料」など)
②情報ソース(資料)を追加する
- 左側のパネルにある「ソースを追加」ボタンをクリックします。
- 情報として学習させたいPDFファイル、Googleドキュメント、YouTube動画のURL、テキストファイルなどをアップロードまたは追加します。
- ポイント: まずは信頼できる資料や、あなたが最もよく参照する資料を1~3つ程度入れて試してみるのがおすすめです。
- 資料の質がAIの回答の質を決めます。
③AIに質問したり、要約を依頼したりする
- アップロードが完了すると、AIが自動的に資料を分析し、要約や重要なポイントの提案がされることがあります。
- 中央のチャットエリアで、資料の内容に関する質問を入力します。
- 質問例:
- 「この資料の主要な3つの論点は何か?」
- 「この章の要点を200字でまとめてください」
- 「資料Aと資料Bの共通点と相違点を教えて」
- 質問例:
- AIの回答には引用元リンクが表示されます。このリンクをクリックして、回答の根拠となった資料の箇所を必ず確認し、AIの回答が正しいか検証する習慣をつけましょう。
さらに上手に使いこなすためのコツ
使い方次第で、貴方の理解が更に深まります。
1. 質問の仕方で回答の質を高める
- 具体的に質問する
漠然とした質問(例:「この資料について教えて」)ではなく、何を知りたいかを明確にします。(例:「この資料で示されている〇〇の市場規模とその根拠は?」) - 出力形式を指定する
「箇条書きで」「表形式で」など、回答の形式を指定すると、情報が整理されて見やすくなります。 - 段階的に掘り下げる
まずは概要を質問し、その回答からさらに詳しく知りたい部分を尋ねるという流れ(例:「まず概要を教えて」→「その中の〇〇についてもっと詳しく」)が効果的です。
2. 整理と活用の工夫
- メモ機能を活用する: AIとのチャットで得た重要な回答や、資料を読んで気づいたことを「ノートに保存」ボタンでメモとして記録しましょう。後からの復習や資料作成に役立ちます。
- タグ付けや命名規則を決める: ノートブックやソース(資料)に「プロジェクト名_目的」などの明確な命名規則を設けると、資料が増えても管理が容易になり、検索性も向上します。
- 複数の視点を含める: 同じテーマでも、異なる意見や視点を持つ複数の資料をアップロードすると、AIがより包括的な分析をしてくれるようになります。
まずは、あなたがよく読むPDFや、見直したいYouTube動画などを入れてみて、上記ステップ1〜3を試すことから始めてみてください。
活用パターン別:具体的な指示のコツ
提供された資料の形式や目的に応じて、AIへの指示を工夫することで、より質の高い回答を引き出すことができます。
1. YouTubeなどの動画から、必要な知識をまとめる
YouTubeのURLをソースとして追加すると、動画の**文字起こし(トランスクリプト)**をAIが解析します。
| 目的 | 活用法と具体的な指示のコツ |
| 全体像の把握 | 長時間の動画を視聴せずに、要点を短時間で把握します。 |
| 特定情報の抽出 | 特定のキーワードや登場人物の発言だけを抜き出します。 |
| 学びの深化 | 動画内容を基に、さらに理解を深めるための問いを立てます。 |
2.PDFやWordなどから、必要な知識をまとめる
論文、会議録、マニュアルなどのドキュメントを情報源として、迅速な検索や分析に活用します。
| 目的 | 活用法と具体的な指示のコツ |
| マニュアル・規定の検索 | 複雑な資料から、必要な手続きや情報を迅速に取り出します。 |
| 学術論文の要約 | 難解な専門用語が多い論文の核心を短時間で理解します。 |
| 会議録の整理 | 長文の会議記録から、決定事項やタスクを明確にします。 |
3. 受験勉強や語学習得に活用する
学習教材をソースに追加し、AIを学習パートナーとして活用します。
| 目的 | 活用法と具体的な指示のコツ |
| 記憶の定着(クイズ) | 覚えるべき知識をクイズ形式で出題してもらい、理解度を確認します。 |
| 概念の理解 | 難解な用語や歴史的背景を、わかりやすい言葉で解説してもらいます。 |
| 語学学習 | 単語帳や英文をソースに追加し、定着をサポートしてもらいます。 |
上級者になるための活用TIPS
- メモ機能の活用: AIの回答や資料を読んで気づいた重要なポイントは、右側の「メモ」に追加し、後で復習できるように整理しましょう。
- 比較分析: 複数の関連資料を同じノートブックに入れ、「資料Aと資料Bの共通点と相違点を比較してください」と質問すると、横断的な知見が得られます。
本日の課題、NotebookLMを実際に使ってみよう
- まずはやってみよう!
- 長いYouTube番組のまとめを作ってみるとか、長文ウェブページの理解の為に出力してみるとか
課題を提出するかどうかは さんの自由!
笑売人になる為には課題提出はやった方が良いよ!